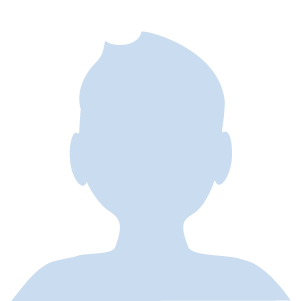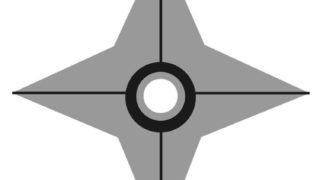今年は新型コロナウィルスで、売上が激減したブロガーの人は多いのではないでしょうか。
そんなブロガーやアフィリエイターにとって、救世主ともなりうる政府の施策。
恩恵にあずかっている人もたくさんいます。
持続化給付金が振り込まれていた…!
(15日申請、26日入金)旅ブロガーの活動資金として、大切に使わせていただきます🙇🏻♀️
海外旅行が解禁されたら旅を再開して、
ブログやSNSを世界の可愛い旅行地の写真で埋め尽くして、見る人の心を明るくするような旅アカウントを作りたい✈︎✨ pic.twitter.com/r927Cl2qgm
— ゆかり@旅ブロガー (@yukari_blogger) May 26, 2020
私も実際に申請をしてみましたが、ブロガーって一体、業種って何になるのだろう・・
実際に相談窓口に聞いてやってみた体験談などを解説していこうと思います。
ブロガーの業種って何になるか聞いてみた!
今回持続化給付金を申請するにあたって、内容を入力していました。
そこで手がとまったのが、「業種」の欄。

ここ、ブロガーって一体何になるのでしょう?
問合せ窓口に問い合わせ
実はこの「業種」
ブロガーとして記事を書いているけれど、ライターではない?
記事は書いているけどブログは運営しているからweb関係?
調べても調べてもわからないので、問合せしてみることにしました。
持続化給付金はコールセンターとLINEで問合せをすることができます。
持続化給付金事業コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570 (通話料無料)
IP電話専用回線:03-6831-0613(通話料有料)LINEアカウント
LINE ID:@kyufukin_line
ここ、土曜日のお昼にかけたけど、なかなか繋がりません。
その都度電話を切られるので、その都度再ダイヤルをする必要があります。
私も再ダイヤル4回でようやく繋がりました。
これはタイミングなので、繋がらなくても諦めず掛けなおしましょう。
場合によってはLINEの方が時間を取られなくて済むかもしれませんね。
「これ」という分類項目はない
コールセンターの担当の人に相談したところ、下のような回答でした。
「こちらでは、仕事内容に対して「この業種です」と確実なことをお答えすることは出来かねます。
お客様の方で、業種を調べていただき、該当する業種をご入力ください。」
それでは、間違えてしまった時に再提出になってしまうんじゃないですか?
とも聞いてみましたが、その質問にたいしては
との回答でした。
つまり、
コールセンターではそういったハッキリした回答ができない
ブロガーの仕事=業種〇〇というものはない
ということでした。
厳密なものではないので
これ!という業種がない、という回答だったので、どう入力すればいいのか、という質問をしてみました。
するとコールセンターの担当者からはこんな回答が。
厳密に合っていなければ通らない、ということではないようです。
ただ、教育業なのに製造業で申請、といった「明らかに誰が見ても違うとわかる分類で申請」では通りませんので気を付けてくださいね。
持続化給付金相談窓口では回答得られず
今回問合せしたものの、持続化給付金のコールセンターでハッキリとした回答を得ることはできませんでした。
コールセンターでは
持続化給付金についての必要書類
自分が申請できるかどうか
申請方法
といった全般的な内容について回答ができますが、個人的なことは個人情報保護のところもあり、答えることができないと言います。
今回のような「私の仕事の業種は何?」という質問ではなく
「業種を知りたいんだけどどこで調べたらいい?」といった質問であれば答えることができるようです。
いろいろな事例を調べてみて、自分なりにこれだ!と言うのを見つけるしかなさそうですね。
税務署もハッキリしたことは言えないかも
ちなみにこれも聴いてみた事です。
「コールセンターでわからないのであれば、税務署に聞いてみてもいいですか?」
担当者の人は少し返事に詰まりながら
とのこと。
情報通信業で提出
結局分類業を調べ、一番しっくりくるものは
情報通信業でした。

大分類は情報通信業
中分類はインターネット通信業で申請してみました。
小分類は必須ではないので、中分類まで入力すれば大丈夫です。
ただ、ブロガーと言っても人それぞれにやっていることが違うので、「絶対にこれが正解!」ということではありません。
ライターの仕事がメイン、と考えるのであれば「執筆業」となり、分類は「著述家業」となります。
解釈の仕方や仕事の内容の比重の割合で様々に変わるのがブロガーの難しいところ。
ただ、ブログ運営をしながら記事を作成し、広告収入を得ている事業で一番しっくりくるのは私なりにはこれだ!と思いました。
確実に申請するために、一度分類を調べてみることをお勧めします!
ブロガーの個人事業主が持続化給付金申請した体験談も
今回私もコロナウィルスの影響で収益が昨年よりガタっと減りました。
そのため持続化給付金を申請しました。
その体験談や申請して感じたことも書いていきますね。
まずは対象者になるか確認
まず、持続化給付金を申請できるかどうかについて確認しました。
持続化給付金を申請できる個人事業主は
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月まで
詳しいことをしっかりと確認しておきましょう。
書類を用意
次に、スムーズに申請をするために、必要書類を準備しましょう。
- 2019年分の確定申告書第一表控え(1枚):税務署の収受日付印押印済
- 所得税青色申告決算書の控え(2枚):青色申告者のみ
- 対象月の事業収入がわかるもの(売上台帳など)
- 申請名義の振込先の通帳とカード
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード表面・写真あり住基カード・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書の表面と裏面(特別永住者限定)
まずは全て揃えてしまいましょう。
全てスマホで撮影し写真データをアップロードしていました。
売上台帳には
- 日付
- 取引の明細(勘定科目)
- 対象月
- 会社名(事業主名)
- 売上金額
- 合計金額
上記の内容以外は入れないようにしましょう。
あくまでも申請の対象月の売上のみを簡潔に載せるようにしましょう。
私はfreeeで登録していたので、freeeから売上台帳をダウンロードしました。
金額を計算
次に、いくら給付金がもらえるのか、金額を算定しましょう。
一番わかりやすい方法は、持続化給付金の申請にある試算シュミレーションで入力してみること。
少し手間ですが、欲しい内容が自動で計算されるため、申請ページに入力するのが楽になります。
新規登録して入力をしていく
そして持続化給付金のホームページにアクセスし、仮登録→本登録に進みましょう。
この時パスワードとログインIDは必ず控えておきましょう。
「ログインできない!」という人が続出しているからです。
サーバーがアクセス集中、他にもいくつか原因が考えられます。
サーバーメンテナンスの時間かもしれません。
持続化給付金の受付完了したってツイートしたら知り合いからめちゃ「ログインできない」とか「書類何がいるの?」って聞かれます。ログインはそのまま進むと止まるので一旦キャッシュを綺麗にして入れ直してやるとできますよ!僕は来たメールから入り直してIDとPASSでログインで出来ました
— リュウ@ローエデ㌠P (@ryu_hyper) May 1, 2020
回線が混みあっている、という事も考えられますので、諦めずにマイページにログインして手続きを済ませましょう。
申請する月がわかった時に申告する
こちらの申請ですが、実は「下書き保存」機能がありません。
そして登録後「次へ」を押した際、エラーがあると全てデータが消えてしまいます。
これで私は何回も入力をやり直しました。
そして、「後々忘れないように今のうちにやっとこ」ということができないので、申請する月が決まったら申請するようにした方が手間が省けます。
必要書類のみを事前に用意しておけば、いざ申請!という時に困ることはありません。
特に確定申告書Bは、受付印がない場合税務署から取り寄せないといけません。
私は控えを郵送し忘れて、後々取り寄せましたが、それでも1か月以上はかかってしまいました。
申請は受付期間中ならいつでも可能です。
そのため、いつ申請してもできるように、書類だけは揃えておきましょう。
初めてだとハードルは高い
今回の持続化給付金。
ネットでの申請などの手続きが初めてだと、少しハードルが高いかもしれません。
実際私はなかなかわからずに時間がかかりました。
そのため、
- マイページを作る
- 書類を集める
- 申請をする
といったように、3段階にわけて申請を行いました。
わかってしまえば簡単ですが、わからないとハードルは高く感じてしまいます。
そういった方のために、「申請サポート会場」が各都道府県に設置されています。
ただ、予約制なので公式ページから予約をしておきましょう!
おわりに
今日は持続化給付金の申請の際、ブロガーの職業分類について調べてみました。
厳密にはコレ!というものがないだけに迷うこともありますが、虚偽の報告さえしなければある程度は大丈夫なのかな、と問い合わせをして感じました。
申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までなので、確定したら早めに申請しておきましょう!
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!