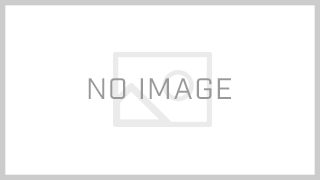スプーン先端のすくう部分の名称は何?持つところなど部位の名前も
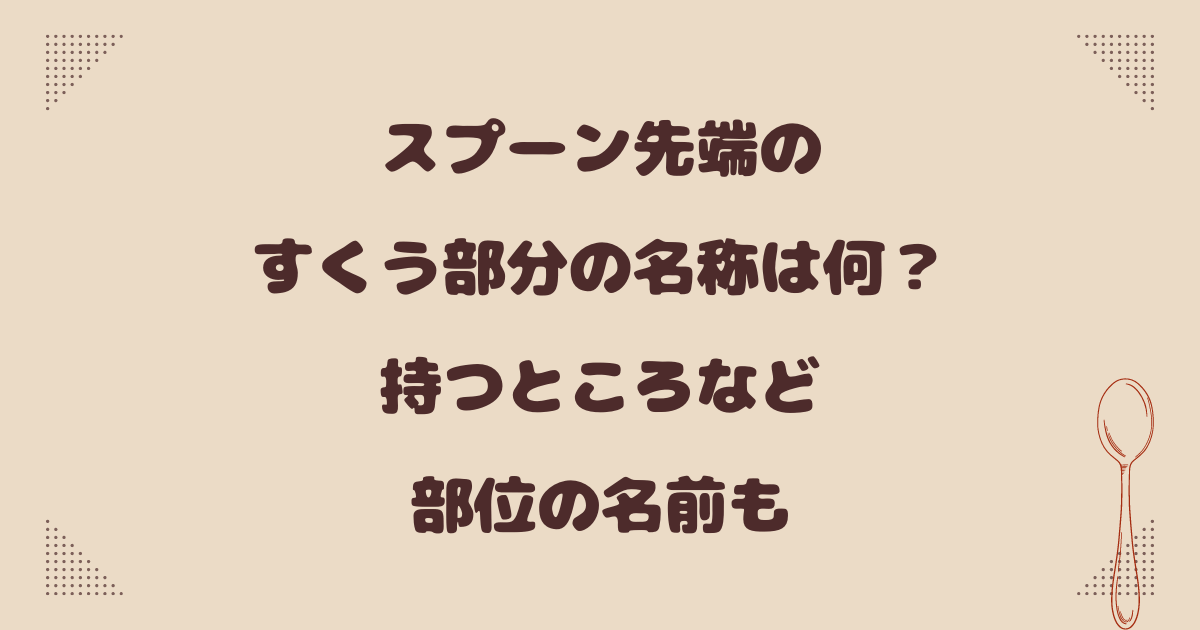
スプーンの丸いところはなんて言う名前?」と聞かれたら、答えることはできますか?
私はできませんでした・・・
毎日使うスプーンの名称、「スプーン」は「スプーン」としてしか認識をしていない人は多いのではないでしょうか。
今日はそれについて調べていきます。
スプーン先端の丸いすくう部分の名称は何?
スプーン先端の丸いところ。
そう、すくう部分の名前です。
ここはなんて名前なのでしょうか?
つぼという名前
こちら、意外な名前がついていました。
「つぼ」という名前です。

つぼ・・・!
つぼのように、液体をためることができるから、というのが語源なのでしょうか。
もともとスプーンは、液体などを計量するために使われていたため、このつぼの大きさや形が、テーブルスプーンやティースプーンは決まっていたといいます。
現在は専用の計量スプーンがあるため、デザインや形も変わってきていますが、使いやすいスプーンは昔と変わらないサイズだったりすることが多いです。
持ち手や他の部位の名称
そして、他の部分の名称も紹介していきます。
- 先端のとがった部分は「先(さき)」
- 持つところは「柄(え)」
- 持つところの先端は「柄尻(えじり)」
という名前がつけられています。
スプーンもその場所に名前がちゃんとついている、ということは、意外とあまり知らないことなんではないでしょうか。
こうやって知ることができると「なるほど~」と思いますよね。
スプーンはいろいろな形がありますが、年齢、利き手で使い勝手が変わります。
せっかく持つなら自分にあった物を選びたいですよね。
ネットショッピングではお店にないこだわりのスプーンなども見つかりますので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね!
↓お得がいっぱいなyahoo!ショッピングで探そう↓
▲ポイントも貯まる&使える▲
スプーンの由来は何?
スプーンはどうして出来たのか、気になる人はいませんか?
実はスプーンはこれまでに様々な歴史があるんです。
発祥は古代
スプーンの由来は古代にまでさかのぼります。
当時料理をすることを覚えた古代人は、木片などを加工して、熱した汁や料理などをよそって使っていたものが時代を経て発展し、現代のスプーンの形になったと言われています。
現実、木片などを使ったスプーンのような道具は二年万前くらいの遺跡から出土しています
また、貝殻や素焼きで作られたとみられるスプーンも発見されているんです。
また、古代エジプトのお墓からは、象牙や骨、なんと黄金で作られたスプーンのような道具が発掘されているので、古代では多くの国でスプーンのようなものが作られていたのではないでしょうか。
スプーンの語源
また、スプーンの語源は、古代アングロ・サクソン語の「かけら」「木片」を意味する「スポンSpon」に由来していると言われています。
ただ、フランス語でスプーンという意味の「キュイエール(cuiller)はmギリシア語で「貝」を意味する「コクロス(kokhlos)」から由来していたことから、貝殻などを材料にしてスプーンを使っていたことが、この言葉からも見て取れますね。
スプーンは古代から私たちと同じように使われていたなんて、時代を経ても同じように歴史の線上にいると思うと嬉しいですね!
スプーンの種類を紹介!
そんなスプーンですが、大きさによって種類が分かれます。
簡単にご紹介していきますね!
スプーンの種類・用途
- サービススプーン(約22cm):大皿から各皿へ取り分ける時使うスプーン
- テーブルスプーン(約20cm): メインデッシュで使うスプーン
- デザートスプーン (約18cm):日本やアジアで食事をする時のスプーン(よく見るのはこちらです)
- スープスプーン (約18cm):皿がきれいな円形のスプーン
- フィッシュスプーン (約19cm):魚の身を食べる時使う 先端に特徴がある
- ティースプーン (約14cm):珈琲など飲むときに使用するもの
- アイスクリームスプーン(約13cm):つぼが浅く平らでアイスをすくいやすい
- コーヒースプーン (約12cm):珈琲を測る時使用する
- デミタススプーン (約11cm):デミタスカップ・ソーサーにつくスプーン
これだけの種類があるのは面白いですね!
コーヒースプーンはよく見ますが、ちゃんと名前があったんですね!
▲楽天ならポイントも使える!クリックしてみよう▲
スプーンも用途でこれだけの種類があるんですね!
これから使う時、「これはなんて種類かな~」と思ってしまいますね。
まとめ
- スプーンのすくうところは「つぼ」と呼ばれる
- 大きさや用途で種類がわかれる
- 古代からスプーンは使われ、アングロサクソン語の「かけら」「木片」を意味する「スポン」からきている
スプーンも何気なく使っているようで、結構奥が深いんですね。
でも、これで一つ知識が増えましたね!
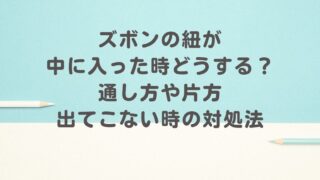
子どもや周りの人がわからなくて困っていたら教えてあげましょう!
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!