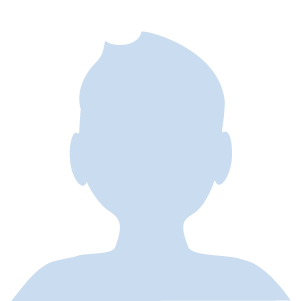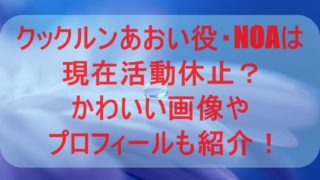今5歳になる我が子。
去年の今頃は「5歳になればオムツも取れてるよね・・・」なんて思ってたのに、5歳になったら全くオムツが取れる気配がない。
なぜ周りの子のようにオムツが取れないんだろうか・・
もしかしたら発達障害なんだろうか?
この記事を読めば、5歳でオムツが外れないのは発達障害なのかどうかと、トイレトレーニングのコツが分かります。
5歳の子どもがオムツが取れないのは発達障害?
5歳の子供が全くオムツが外れる気配がない。
気長に待っているものの、トイレで全くする気がしない・・・
来月は下の子の誕生日‼
5歳になるが、オムツ外れない😢
気長に待つしかないかな⁉— にいな (@4z1gnS0FGn78KR2) July 7, 2019
周囲の子がパンツに切り替わっていくなかで、自分の子どもがオムツが外れないとなると不安な気持ちになりますよね。
ここでは、発達障害の定義も踏まえ解説していきますね。
一概に発達障害とは言えない
5歳の子どもでオムツが取れていなくても、発達障害であるとは断定できません。
そもそも、発達障害とは何かを分かりやすくいうと、
同年代の子と比べて成長や能力が遅れている状態
をあらわしています。
言葉の通り「発達に何かしらの原因で障害がみられる」とのことなんですね。
今は昔よりも検査体制が整ってきたこともあり、発達障害と診断される子どもも増加傾向にあります。
平成5年は13000人と診断された発達障害児が、平成25年には80000人に近い数字になったという研究結果もあるんですね。
ただ、発達は一律、「〇才になったらできる」というものではありません。
スムーズにできる子もいれば、ゆっくりと成長していくと言う子もいます。
大切なことは、あなた自身が落ち着き現状をよく観察することです。
成長には個人差がありますので、あまり深く考えすぎず我が子の成長を見守りましょう。
発達障害の特徴とは
発達障害にはいくつもの種類があります。
- 自閉スペクトラム症(ASD):対人関係や他の人とのやり取りが上手くできない
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD):不注意・多動・衝動性な行動をする
- 学習障害(LD):聞く、話す、読む、書く、計算いずれかの習得や活用が困難
- チック障害:自分の意思関係なく体のどこかが動いてしまう
- 吃音(症):言葉がスムーズに話せない、出てこない
などに分類されることが多いです。
それぞれの学習障害によって、症状が異なります。
例えば「自閉スペクトラム症」は言語の発達の遅れやコミュニケーションの障害が症状として現れます。
また、「注意欠陥多動性障害」に関しては、子どもの年齢に見合わない多動や多弁や不注意行動がみられ、また衝動的な行動も目立つようになります。
一人で複数の症状を持っていることもあるというのも学習障害の特徴です。
オムツ外しができないのと発達障害は直接的な関係はない
発達障害かどうかを自分で確認するチェックリストというものがありますが、その中に
「オムツが外れない」という項目は含まれていません。
どちらかというと
- 同じことを繰り返す「こだわり」が強い
- 嫌だと思う事に対する癇癪が激しい
- 自分の話だけをする
- 相手の話を聴いていない
といった、コミュニケーション力や自分の行動に対する感情などに関するチェック項目が多いです。
ということは、オムツ外しができないことと、発達障害は直接的な関係性はないと思われます。
オムツ外しにたとえるのならば
- オムツを外すと癇癪を起す
- 同じオムツを履こうとする
といった
オムツが外れないことよりも、オムツを外した時の行動やそれに付随する子どもの意識という事の方が重要です。
一度チェックリストを見て子どもの行動を確認してみるようにしましょう。
心配なら病院にいこう
チェックリストには当てはまらない。
ただ、オムツが全く取れる気がなく、今後もどうなるのかがわからない。
どうしても発達障害なのか心配ならば、受診するのが最も有効な手段です。
悶々としているのであれば、一度専門機関に相談してみるのも一つの方法です。
専門病院だと不安…という方は、保健所の方に相談してみるのも一つの方法です。
ただ、たとえ我が子の成長が周りと比べて遅れていたとしても、それを負い目に感じて叱るのは避けるようにしましょう。

子供も精神的な負担を感じてしまうと、成長に影響してしまい、発達が遅くなりかねないのです。
早い段階で受診を検討することも、子の発育をサポートする手段の1つなのではないでしょうか。
子どもが嫌がらない外し方のコツ
5歳にもなったらやっぱりオムツは外していきたいと思いますよね。
小学校が少しずつ目前に控えてくるので、やはりオムツ外しは少しずつ進めていきたいですよね。
少しでもスムーズに進むように、5歳の子供がオムツ離れをするコツについても書いていきますね!
成功体験を与える
こちらはやはり成功体験を少しずつ経験させるのが、オムツ外しがスムーズにいくコツです。
きょーかおめでとんこつらーめん💓🍜
現在5歳の弟がそろそろ完全にオムツ離れしそうなのでおしり拭き余ってるからいつか届けに行くね。消耗品は腐るほど必要だよな。💃— まり☻ (@RY_xxx9) March 18, 2017
成功体験を与えることによって、「自分にもできるんだ!」という達成感を与えることができます。
成功体験を与えることと失敗しても怒らないことです。
簡単なようで意外と見落としがちな点ですので、しっかりチェックしてください。
成功したらちょっとご褒美
トイレに座れる
決まった時間にトイレに誘導
トイレでの成功体験この3つが出来るようになってくると、昼間のオムツ外しはゴールが見えてきます!
のんびり行こう😙
— ふうこ@3児連れのシンママ (@fuko_hahakolog) June 29, 2019
子どもは何かを達成した時に、初めて成長します。
トイレへ行くことに成功したら、おやつや好きなおもちゃを与えるなど成功体験を感じさせましょう。
成功したら褒められることが分かれば、より積極的になれます。
失敗しても当たり前
トイトレは毎回成功することはありません。
それ!まだまだ未就学児の間はトイレの失敗も当たり前、洗濯すればいいし、オムツでもトレパンでもなんでもいいからお母さんと子供が笑顔でいられるほうが大事!👍✨
— きりんさん屋さん (@kirin_san83) June 16, 2019
人間ですから未経験のことで失敗するのは当たり前のこと。
ましてや5歳なら失敗するのは当然なのです。
失敗して掃除するのは大変で、ストレスが溜まる気持ちも分かりますが、むやみやたらに怒ってしまってはお互いにとって良くありません。
ちなみに私は一度激しく怒ってしまったことで、トイトレが全く進まなくなってしまった事がありました。
もし怒ってしまった場合は、子どもにその後ちゃんと謝罪して、自分のペースで少しずつ頑張ろうという事をつたえるようにしてみましょう。
こどもは失敗を繰り返して成長していくので、失敗を責めずに温かい目で見守るようにしましょう。
大事なことは、失敗してもちゃんと笑顔でいられるように準備しておくことです。
タオルはよく乾くものにしておくと、いつでもふかふかのタオルで子どもを一緒抱きしめてあげられますよ!
↓吸収力がスゴイ!トイトレの強い味方↓
▲ふわふわ軽いタオルの種類はこちらをクリック▲
遊びやゲーム感覚でトイレに誘導しよう
少し特殊な方法ですが、ゲーム感覚を楽しみながらであればトイレに行きたいという子どももいます。
自宅で宝物探しをしてトイレにシールを置いておくことなんかは、非常に分かりやすい良い例です。
また、トイレに行けたらご褒美にシールを貼るなどすると、達成感が得られるので喜んで子どもがトイレに行くようになります。
これは子どももやる気になりますよね~!
トイレに行く習慣付けにもプラスの効果を発揮しますよ!

5歳のトイレトレーニングについても紹介!
5歳になっていよいよ少しずつ小学校入学がチラついてきます。
そろそろトイレトレーニングを始めないと・・・
でも5歳はしっかりと自分の意思が主張できる年齢。
トイレトレーニング…
もう5歳やけど、出来るやろか?(笑)— sakkun (@torres_sakkun) July 20, 2017
果たしてできるか?と不安になりますよね。
そこで、5歳の子どものトイレトレーニングでおすすめの方法をご紹介します。
実体験を踏まえた内容ですので、参考にしてください。
寝る前にトイレに連れていこう
夜間帯のおもらしが多い子は特に、寝る前には必ずトイレに誘導してあげましょう。
日課を決めることで、自然とトイレに行くのが当たり前となってきます。
本格的なトレーニングという意識でなく「おもらししないようにトイレに行きたい」と自発性を誘導することができれば、一番理想的ですね。
もしでなくても、トイレに座らなくても、「トイレにいく」という習慣がつけられれば、そこから
なんて誘うことも出来ます。
こどもはふとしたきっかけやタイミングで「やってみようかな」と思うものです。
怖がらせない工夫も
これは私の実体験なのですが、幼稚園や保育園のトイレではしっかり出来ても、家になると途端にできないことってあります。
それはなぜか聞いてみると「トイレが高くて怖いの」ということだったのです。
そのため、私がやってみたことは
- トイレに好きなキャラクターのおもちゃを置いておく
- トイレをカラフルにして楽しそうな雰囲気にする
- トイレの踏み台を上りやすいものにする
ということ。
この中で特に効果的だったのは
好きなキャラクターのおもちゃやトイレグッズをトイレに置く
というもの。
と誘っていたものです。
また、トイレにまたぐときの踏み台も、本当にものによっては助かるので、ぜひ一つあるといいですよ!
お気に入りのパンツを使おう
トイレトレーニング中はトレーニングパンツを使う事が多いです。
その時シンプルな物ももちろんいいんですが、アニメやヒーローキャラクターなど、本人が好きな絵柄のものをチョイスするのがコツです。
お気に入りのパンツを購入しておけば「汚したくない」という心理が働き、自らトイレに行くようになる可能性があります。
時間が合えば子どもと一緒にパンツ選びをするのが良いですね。
おわりに
5歳の子どもがオムツが外れないのは、一概に発達障害とは言えないという点とトイレトレーニングのコツをご紹介しました。
まずは冷静に子どもの状態をよく見て適切な行動をするように、あなた自身が心掛けなくてはなりません。
焦らず子どもと向き合うことで、はじめて解決策が見えてくるものです。
夫婦や周りの人と協力しながら、親子のペースで進めていけるといいですね。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!